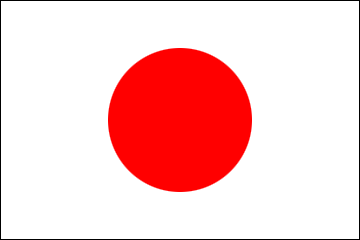一村一品運動アドバイザーへのインタビュー
平成29年3月23日
2013年11月より、JICAを通じて個別専門家としてエルサルバドルの国家小零細企業委員会(CONAMYPE)に派遣されている内河友規さん。日本の経験に基づく「一村一品運動」を当国に普及させ、人々の生活向上及び国の発展に大きく寄与してきました。このような活動を通じ、エルサルバドルにおける日本の国際協力の推進、両国の友好関係の増進に、顕著な功績を残していることが高く評価され、2017年3月22日、田良原大使より、内河さんに対し、「在外公館長表彰」が授与されました。
受賞者の内河さんにインタビューを行いました。
●内河さんは一村一品運動アドバイザーとしてエルサルバドルに派遣されているとのことですが、一村一品運動とはどのようなもので、内河さんはどのようなお仕事をしているのでしょうか。
一村一品運動(英名略称OVOP)は、1970年代に大分県の故・平松元知事が同県地場産業振興政策として創始された事業で、地域の資源を活用し、地域ブランド化を図りつつ、特産品の開発や販売促進、更には地域に根差した人材の育成や地域自尊心の回復、地域経済の再活性化を目指すものです。
私はJICA専門家としてCONAMYPEに派遣され、大分県発祥の同運動のコンセプトを、エルサルバドルの政府職員や地域生産者に伝えつつ、当国の政治・経済・社会・文化的背景に即した形で適応するような当国オリジナルのOVOP実施制度・体制作りへの助言、支援を行っています。
また当国OVOPが地域経済に果たす社会・経済インパクトの分析と評価を行い、同運動が適切に運営され、課題の解決手法が導出されるような政策・技術的支援も行っています。
●エルサルバドルにおける一村一品運動のこれまでの成果とその要因についてお聞かせください。
当国OVOPの成果としては、2010年のOVOP事業導入以来、既に全国82市でOVOPコンセプトの普及・啓蒙が図られ、OVOPを主体的に運営する地域別委員会が42市で設立され、各種OVOP活動が実施されていることが挙げられます。またこれら地域別委員会の連合である全国OVOPネットワークが設立され、さらにはCONAMYPE内にOVOP局が設置されるなど、体制面での拡充が特記されます。 また政策面でも、2016年10月にはOVOP事業の政策的支柱となる「OVOP国家政策」が策定・公布され、その継続性が担保されたことから、OVOPが制度・政策面でも当国の地場産業振興の重要な活用事例となっていることが示されています。 |
|
| 一村一品全国物産展に参加する オルティス副大統領(中央)、 ロヘルCONAMYPE長官(右) |
当国においてOVOPがこのように受け入れられ活用されている要因としては、日本の過疎地域と同様、当国が主要な産業や鉱物資源などに恵まれず、人材の外部への流出など地域経済の疲弊と地域コミュニティ意識崩壊などの危機に直面しており、その打開策として、OVOPに着目されたことが挙げられます。
地域資源を「モノ」のみに捉えるのではなく、そこに住む「人」や自然環境、伝統、文化、歴史など「コト」も重要な資源として捉え、地域住民(生産者)が主体となって、地域資源の価値を再発見し、地域ブランドや地域特性などの付加価値を与え、販売・プロモートする。このOVOPの基本コンセプトが、人材流出に危惧する当国政府や地域生産者の琴線に触れ、従来の海外投資や外部経済に頼らない地域経済開発事業として、積極的な導入に繋がったものと考えます。
またこの点が最も重要なのですが、OVOPを国の施策として実施するCONAMYPEが、長官を筆頭に各地の職員に至るまで、そのコンセプトをしっかり理解し、自国の文脈に沿う形で応用させたこと、また地域生産者の自主自立の精神を育成しながら展開を推進してきたことこそが、現在の成果実現を後押しした最大の要因だと思います。
●内河さんの特にお勧めの産品を二つほどご紹介ください。
●最後に、内河さんにとって、「国際協力」とは。
私自身、長崎の地方出身で、幼少期から都市部への人材流出、過去の原爆投下の戦禍や経験談に触れ、また雲仙普賢岳の噴火災害にも遭遇するなど、先に述べた地域経済の疲弊を身近に体感しながら育ちました。また、学生・社会人時代を過ごした関西では阪神・淡路大震災を体験するなど、自然災害の脅威にも触れて来ました。
しかしそれら地域経済の疲弊や戦禍、自然災害の傷跡からも、人智や地域共同体の連帯を通じて復興を成し遂げてきた日本の地域の活力や知恵や経験を、同じような状況に苦しみつつも前途に向けて進む途上国の発展に役立てられるのが「国際協力」と考え、その思いに基づき尽力しているところです。
ですが日本で育まれたコンセプトや手法を闇雲に押し付けるのではなく、各国の特性や環境を受け入れるような柔軟な対応と適応力も求められます。時として日本では思いも付かないような新たな産品、制度や手法が生み出される瞬間に立ち会え、それが日本の制度・体制改善や人材育成にも繋がると言う相互共益の活動が出来ることも、私にとっての「国際協力」であり、関わることの醍醐味だと考えております。
●ありがとうございました。
| 当国お勧めの産品は農産物加工品、民芸品など多くありすぎて紹介に困りますが、特に二つ選ぶとすれば、西部アウアチャパン県のサンロレンソ市や中部サンビセンテ県のサンビセンテ市がOVOP特産品として生産する中米原産のホコテ(カシューナッツ科果樹)の果実の加工品(ジャムやリキュール)と、また同サンロレンソ市が中心となって生産する同じく中米原産のロロコ(ツル科植物)の花の芽の加工産品(ペーストやパスタソース)です。 |
ホコテ
|
|
| 栄養分 |
|
ロロコ |
●最後に、内河さんにとって、「国際協力」とは。
私自身、長崎の地方出身で、幼少期から都市部への人材流出、過去の原爆投下の戦禍や経験談に触れ、また雲仙普賢岳の噴火災害にも遭遇するなど、先に述べた地域経済の疲弊を身近に体感しながら育ちました。また、学生・社会人時代を過ごした関西では阪神・淡路大震災を体験するなど、自然災害の脅威にも触れて来ました。
しかしそれら地域経済の疲弊や戦禍、自然災害の傷跡からも、人智や地域共同体の連帯を通じて復興を成し遂げてきた日本の地域の活力や知恵や経験を、同じような状況に苦しみつつも前途に向けて進む途上国の発展に役立てられるのが「国際協力」と考え、その思いに基づき尽力しているところです。
ですが日本で育まれたコンセプトや手法を闇雲に押し付けるのではなく、各国の特性や環境を受け入れるような柔軟な対応と適応力も求められます。時として日本では思いも付かないような新たな産品、制度や手法が生み出される瞬間に立ち会え、それが日本の制度・体制改善や人材育成にも繋がると言う相互共益の活動が出来ることも、私にとっての「国際協力」であり、関わることの醍醐味だと考えております。
●ありがとうございました。